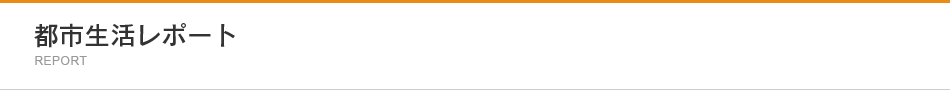
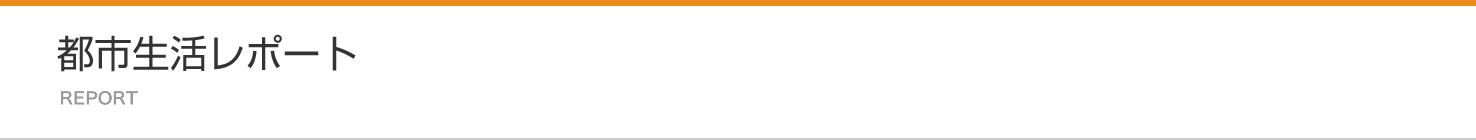
| カテゴリ | 住まいと暮らし 環境・エネルギー |
|---|---|
| 発行年 | 2025年02月 |
| 作成目的 | 2024年1月の能登半島地震や同年8月の南海トラフ地震臨時情報の発表など、改めて防災への意識が高まる出来事が続いています。首都直下地震の発生確率は依然として高く、首都圏住民にとって災害への備えは喫緊の課題となっています。そこで、災害への意識や実態、特に在宅避難とエネルギーの備えに着目し、防災意識を高め、防災行動を促進するためのヒントをご紹介します。 |
| 内容要旨 | ◇災害経験や報道が「備え」のきっかけに ・備えのきっかけとして、災害報道に触れたことや東日本大震災の経験が最多 ・約4割が、南海トラフ地震臨時情報の発表で、「災害をより自分ごととして考えるようになった」 ◇「備えができている」人は2割程度 ・約5割の人が防災に関心がある一方で、「備えができている」と自己評価している人は2割程度 ・特に、女性や若年層で「何を備えたらよいかわからない」と回答した割合が高い ◇特にエネルギーは、水や食料に比べて備えられていない ・「電気」や「ガス」を備えられている人は1割程度 ・半数以上が「電気の備えは難しい」と感じている ◇暑さ・寒さ対策の実施率は低い ・災害時の「暑さ対策」をしている人は1割程度 ・何をすればよいかわからず、難しさを感じている ◇災害対策として、発電・蓄電への関心が高まる ・発電・蓄電機器の所有率は低いが、30代の関心は高い ・蓄電池は、メリットの理解が進むと、導入意向が高まる可能性 ◇住まい選びで「防災」を重視する傾向 ・若年層ほど、住まい選びで建物や土地の防災を重視 ・集合住宅は賃貸や築年数が古いほど「備え」の実施率が低い ◇備蓄のニーズはあるが、スペースに制約 ・「日常的に使えるもので備えたい」が、スペースの制約で備蓄できていない ・ローリングストックの認知率・実施率は低く、メリットが浸透途上 ◇レジリエンス度が高い人の備え ・レジリエンス度が高いほど災害時の生活をイメージできており、メンタル面も重視 ・レジリエンス度が高いほど「電気は自分で備えるべき」と考えている |