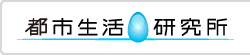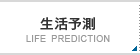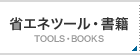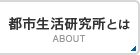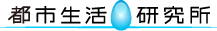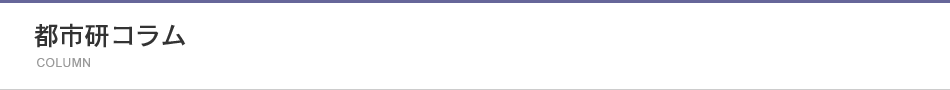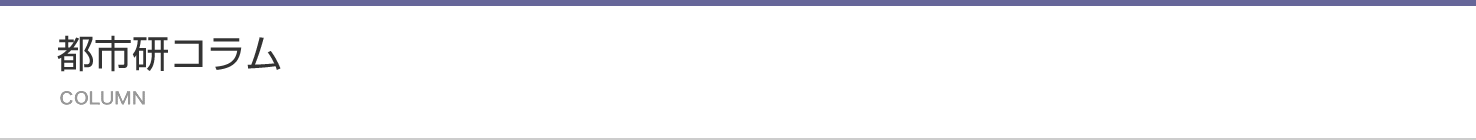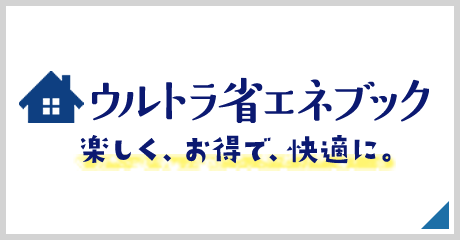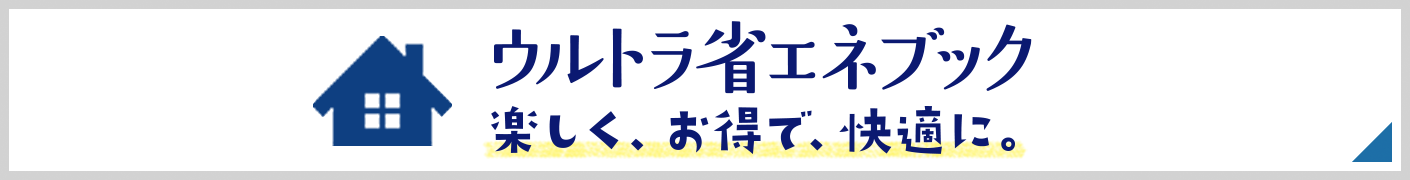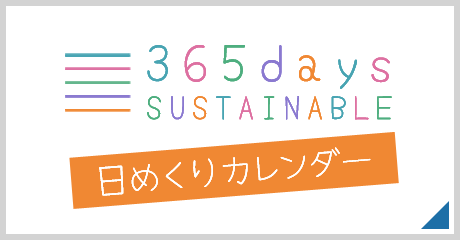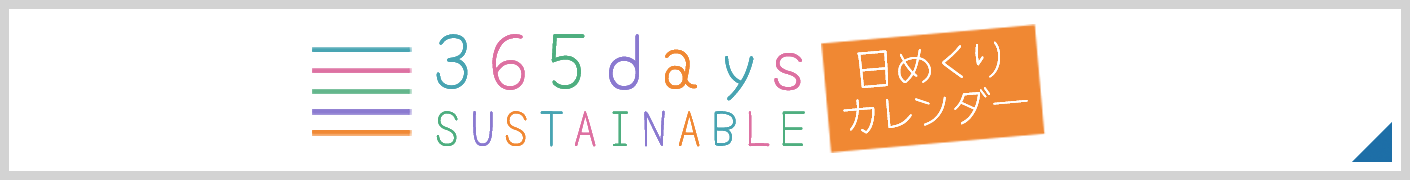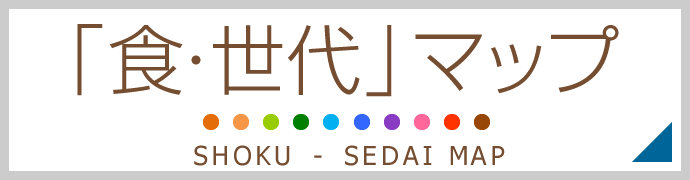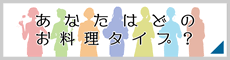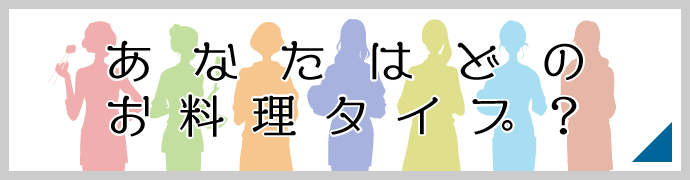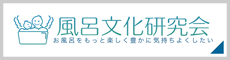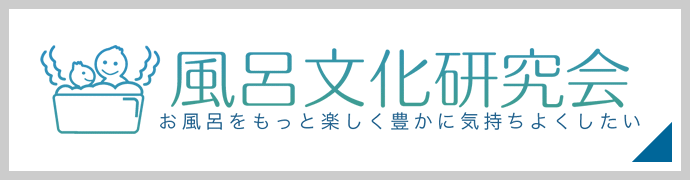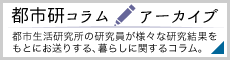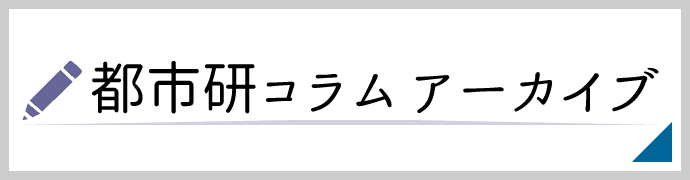中学生は、親の保護から自立へと向かって個人の生活領域を広げる時期に差しかかっています。また、彼らの親も働き盛りの年代であり、中学生のいる家庭は、家族それぞれの生活時間がバラバラになるライフステージに位置しています。このような状況の中、中学生がどのくらいの頻度で家族と一緒に食事を摂り、そのような共食の実態についてどのように感じているのか、調査結果(注2)よりご紹介したいと思います。
(1)家族の共食の実態
◆夕食時に家族全員が揃うのは「週1−2回」
中学生たちに、家族全員で食べる"共食"の頻度について尋ねると、朝食の場合は「ほとんどない」(40.2%)が最も多く、次に多いのが「週1−2日」(28.3%)です。それ以上は4人に1人に留まります。夕食では、「週1−2日」(41.3%)が最も多く、「ほとんどない」という人も7.5%いました。


また、夕食時に父だけが揃わないことが「よくある」と答えた人は55.3%で、「時々ある」(27.6%)を合わせると8割を超えます。父が家族の共食頻度に大きな影響を与えていることが分かります。したがって、家族全員が食卓を囲む機会は、父も揃う休日などに持たれていると推察されます。
一方、"孤食"については、夕食を一人で食べることがあると答えた人は3割で、2割は週1回以上あると答えています。また、学年が上がると孤食の頻度が増加しますが、これは塾や部活、友人との付き合いなど独自の生活領域が学年と共に広がるためと考えられます。
(2)共食に対する意識
◆食事中の会話は楽しいし、家族と共食する機会を増やしたい食事中家族とよく話をすると答えた中学生は8割で、主な話題の上位5位に、1.学校のこと、2.テレビのこと、3.友だちのこと、4.遊びのこと、5.勉強のこと、があげられています。このような食事中の会話を、約9割の中学生が楽しいと感じています。
「家族が、休日などにできるだけ揃って食事をする機会を持とうとしている」と答えた中学生は約8割で、「共食の機会をもっと増やしたい」と望んでいる人は6割を超えています。


以上より、中学生のいる家庭では、家族が揃って共食することは主に休日などに行われている状況ですが、多くの中学生が食事中の家族との会話を楽しいと感じ、共食の機会をもっと増やしたいと望んでいました。また、共食頻度を減らす要因として、父だけが揃わないことがあげられ、父の帰宅時間に問題があるといえます。以前、筆者が行った中高生のアンケート調査(2000年実施)でも、家族との食事について、6~8割の子どもが「楽しいおしゃべりをしながら食べたい」(79.8%)、「家族が揃って一緒に食べたい」(72.4%)、「父も早く帰ってきて、一緒に食べてほしい」(60.0%)、「一人の食事はつまらない」(59.6%)と感じていました。
こうした子どもの気持ちに応えるためには、実際には共食機会が限られていても、親が食事を楽しいコミュニケーションの場として大切にしているという姿勢を示すことが重要であり、会話を通じて子どもとの信頼関係をいかに深めていくかが問われていると考えられます。
注1)本稿の内容およびデータは、報告書『家庭における食事環境と中学生の幸福感』東京ガス都市生活研究所(2005年4月)から抜粋。
注2)東京圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)に住む中学生約2000人(有効回答数720人)を対象にした、郵送法によるアンケート調査。2004年12月実施。